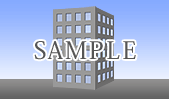通関士試験学習法 管理人おすすめ
管理人が実際に通関士の試験を受けた時の学習法を公開します!
6月(試験4か月前)勉強スタート
試験を受けようと思ったのは早かったのですが、重い腰を上げたのが6月。通関士とは全く関係のない仕事をしていましたし、知識もゼロからのスタートでした。ちょっと遅いかなと思いましたが、思い切ってある通信講座を受講。
まずはざっとテキストに目を通し、全体の流れを把握しました。
下記の試験科目と配分をご覧ください
【通関業法】
・選択式・・・30点(10問)
・択一式・・・10点(10問)
【関税法】
関税法、関税定率法その他関税に関する法律および外国為替および外国貿易法(同法第6章にかかわる部分に限る)
・選択式・・・35点(15問)
・択一式・・・15点(15問)
【通関書類の作成要領その他通関手続きの実務】
通関書類の作成要領
・選択式・計算式・・・15点(2問)
その他通関手続きの実務
・選択式・・・5点(5問)
・択一式・・・5点(5問)
・計算式・・・5点(5問)
一番比重の高いのが関税法、次に通関業法、通関書類の作成要領その他通関手続きの実務と続きます。
私は、出題割合が高く重要と思われる関税法から勉強を始めました。
※通信講座のテキストは長年の蓄積されたデータから試験に出題されそうな重要ポイントを効率よく勉強できます。
通信講座とは別に過去5年間の問題集を購入し、「試験までに5回解く!」ことを目標にしました。
7月(試験3か月前)過去問2回目
関税法からはじめて通関業法に突入。通関業法は比較的簡単(私には)だと感じたので、ポイントを押さえながら過去問を繰り返し解くことに専念。
同時に通関書類の作成要領・・・も勉強開始。
過去問問題集をおすすめするのには理由があります。
それは答えがそのまま試験に出る重要ポイントだからです。時間がない人は過去問の答えを覚えていくという裏ワザもアリです♪
8月(試験2か月前)過去問3・4回目&予想問題集
通関書類の作成要領・・・の勉強が終わったら、自分の苦手な分野を強化。私はやはり関税法だったので、関税法をおさらいしつつ、過去問3回目、4回目に突入。
この辺りからかなりすんなり問題が解けるようになりはじめました。
次に予想問題集を購入し、試験までに2回解くことを目標に頑張りました。
※検索窓に「通関士」と入力して検索してみてください。結構出てきます。
9月(試験1か月前)過去問5回目&予想問題集&模擬試験
ラストスパートです!もう一度過去問を最初から解きます。
通信講座を受講していれば、1ヶ月前くらいになると模擬試験を実施しているところもあります。
その結果を元に苦手分野を克服。
独学の場合は予想問題集に取り組みましょう。
10月初旬 試験本番!
ここまで来たらあとは体調を整えるだけです。例年10月初旬に行われますので、10月に入ったらスグです。
全国13か所で行われるということは、他県で受験する人も多いでしょうから、できれば当日迷わないように試験会場の下見をしたり、家やホテルからどのくらいかかるかを確かめておくと安心です!
最後になりますが、一発合格を目指すならある程度勉強に時間を割いてください。
そんなに難しい資格ではありませんが、ちょっと勉強しただけで合格するような資格でもありません。
私は仕事をしながらでしたので、夜はなるべく早く寝て、朝4時くらいから出勤時間までと、土日は図書館で5時間くらい勉強していました。特に夏は図書館が涼しくておすすめです♪
以上が管理人おすすめ学習法になります。
参考になったかどうかわかりませんが、とにかく一発で合格できるように頑張ってくださいね!